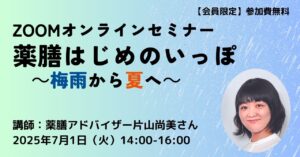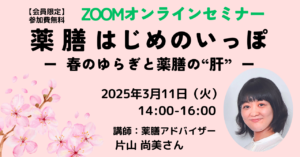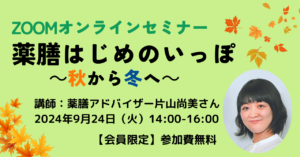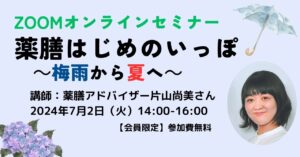フォトグラファーのむーちょこと、武藤奈緒美です。
年明け早々の会津(福島)、横手(秋田)、十日町(新潟)への取材旅。この3ヶ所に共通するのは豪雪地帯であること。前回の会津行きに続き、今回は横手を訪れて見聞きしたことをお届けします。
初めて横手を訪れたのは東日本大震災の前年の3月でした(あの震災が起きてからこっち、2011年が記憶の間仕切りのようになって、震災以前か以後かで出来事を記憶している気がします)。
日暮れの電車移動で、車窓から見えていたのは延々と続く塗り壁のようなもので、何かしらの施設を囲う塀なのか、それにしてもかなり大きい施設だなと漠然と眺めていたのですが、下車してようやくその正体が判明・・・雪の壁でした。
その横手へ雪国の暮らしを取材するという目的で再訪しました。ただただ雪の壁に仰天するだけだった初回から一歩踏み込んで、横手を知る機会の到来です。
会津での取材を終えた足で郡山に向かい、東北新幹線やまびこで盛岡へ、そこでこまちに乗り換え花火で有名な大曲で下車、在来線で横手へ。着いたときは19時を過ぎていました。
かつておののいた雪の壁はみあたらなかったものの、駅のロータリーを囲むように雪が寄せられていました。会津もそうでしたが横手もさほど寒くありません。我が家の備品でできうるかぎりの防寒対策をして乗り込んだので拍子抜けしたものの、降るときは降るところなのだということは寄せられた雪の量で一目瞭然です。

横手での取材撮影のメインは郷土食に関するものでした。有数の米どころで、タクシーから見えるどこまでも続く雪原の下は田んぼなのだと運転手さんが教えてくれました。盆地の中でもいちばんの耕作面積なんだよ、とも。
最初の取材先のこうじ屋さんで何度も「ここは米があるから」とおっしゃるのを聞きました。この辺りはみんな米を作っていて、うちは近隣から米と大豆がもちこまれ、そこに米こうじを加えて仕込み味噌を作り各家庭に戻す。その仕込み味噌はその家の菌で発酵し熟成されてその家の味になる、と。
こうじ屋さんは米こうじをこしらえるのが主な仕事で、ほかに味噌や甘酒などの加工品も作っているとのこと。大豆は秋田のリュウホウを使用。国産どころか地場のものを使っているということがもうありがたい。巷には外国産の大豆を使った製品があふれ返っていますから。

こうした取材で食料自給の話を伺うとつい、例えば47都道府県で鎖国になったとして…と思い巡らすのが私の常です。秋田は主食の米がある、大豆がある、野菜も作っている、海があるから魚がとれるし塩も作れる。鎖国となったらきっと強い。ちなみに私の故郷・茨城もおそらく鎖国に強いはず。首都圏という大きなマーケットのそばであらゆるものを生産する農業県だし海に面しているから。その茨城と横手のある秋田は縁が深く、関ヶ原の合戦ののち常陸(茨城の旧国名)を治めていた佐竹氏は秋田へと転封になり、その際常陸の国の美人を引き連れて行ってしまった、なんて話がまことしやかに残っています。
ほかに米の加工品・干し餅の生産過程も取材しました。
米を炊き潰して伸ばしのし餅状にして乾燥したものを、小さくカットして藁の紐で繋ぎ、さらに乾燥を重ね、いわば餅の干物が出来上がります。気温が下がり乾燥しないと出来ない冬の仕事なんだそうで、12月に取材予定でしたが気温が下がりきらなかったので1月に変更になったのです。こうして冬の仕事が出来たことで出稼ぎに行かなくても大丈夫になったと伺いました。

干し餅を見て思い出しました。
おととし、古民家リノベーションの手伝いに出かけた際に、作業に来ていた初老の大工さんから「食べてみる?」と渡された花札よりもひとまわり程小さい白い板状の堅い食べ物が干し餅で、農作業の合間に小腹が空いたらこれをつまむんだと教えてもらいました。食べるとするかしないか程の淡い塩味で、味わうというよりもカロリー補給第一の保存食という感じ。非常食にも向いてそうです。
取材先ではこの干し餅をさらに加工したおかきも作っていました。米粒を噛みしめるような食感が後を引く素朴な風味に、帰りの新幹線で食べる手が止まりませんでした。
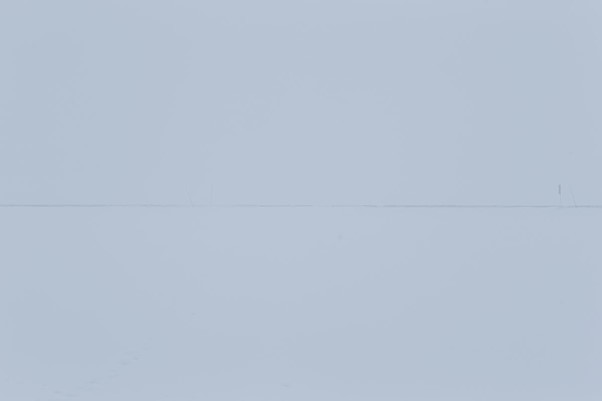
取材を終え駅に向かうタクシーから雪原を眺め、こうじ屋さんが「田植えの時期にこの辺りを空から見ると、集落が島みたいに見えるんですよ」と話していたのを思い出していました。
田んぼに水が入って空を映す風景や稲穂が垂れて黄金色に輝く風景を目の前の雪原に重ねて想像し、雪国横手の暮らしが米と分かちがたいものだということを目でも舌でも実感しました。もっと米を食べよう。今の味噌が切れたらこうじ屋さんの味噌を取り寄せよう。干し餅おかきを買えるところも探さねば・・・次の行き先、十日町に続きます。